モノづくりはとっても楽しい。
モノづくりの深みにハマると、普段使っている素材のことが気になってきます。
皮はどうやって革になり自分のところまで届いているのか、どんなふうに加工しているのか。
インターネットでももちろん調べることはできますが、やっぱり気になることは足を運び、自分の五感で確認したいですよね。
ってことで行ってきました工場見学!
なかなか工場見学が少ないジャンルではありますが、そんな中で良心的にも月に1度定期的に工場見学を開催しているのが、東京は墨田区にある山口産業株式会社さんです。それでは当日の流れに沿って一部始終を余すことなくお伝えします。
※サイト更新忘れでデータが消え、画像がなくなってしまいました。申し訳ないですが、文字情報だけの提供となります。いつかもう一度行って写真素材を調達したいです。
山口産業ってどんな会社?
さて無事に辿り着きましたので、ここで山口産業がどんな会社なのかについてご説明します。
山口産業は皮から革にする工程、「なめし」やなめした革の染色・仕上げ加工を行っている皮革製造業者です。
皮はそのままでは使えません。皮も生ものですので、何の処理もしないとお肉と同様みるみる腐ってしまいます。
その皮に処理を施すことで「皮から革」にし、生活の中で使えるものにしてくれるのが山口産業なのです。
予備知識ですが英語ではなめすことを「tan」と言うため、なめしを担っている企業のことを通称「タンナー」と呼びます。
取り扱っている革は基本的に豚革ですが、最近ではMATAGIプロジェクトというものを開始し、地方で駆除されてしまったイノシシやシカの皮なめしにも力を入れています。このMATAGIプロジェクトには非常に共感したので、本記事末尾で詳しく説明します。
また代表の山口さんが来場者の写真撮影やメディアへのアップロードに非常に寛容であったこと、墨田区の児童対象で年間に600人もの人数を工場見学に受け入れていることは印象的でした。
この工場見学会は「やさしい革の話」という名前がついているのですが、山口産業自体が「やさしい」印象を受けました。
いざ工場見学
無事山口産業に辿り着いた私。
入り口にはこんなものが。なになに・・・。
「ご来場ありがとうございます。開始時刻まで工場前にてお待ち下さい。」
「工場見学パンフレットです。ご自由にお持ちください。」
じゃあ遠慮なく頂きましょうとも。
パンフレットはこんな感じ。
裏側にはなめしの工程が写真付きで説明されています。
そして時間ピッタリに登場されました。このナイスミドルな方が山口産業の代表取締役で本日の案内人、山口明宏さんです。
なめし業者の社長さんってもっとゴツい感じの方をイメージしていましたが、非常に清潔感のあるスマートな方でした。
実際の工場見学に移る前に、現在の山口産業での取り組みや取り扱っている豚革の原料事情などを10分程度説明して頂きました。
その時に教えて頂いたことは
・年間の豚革流通量は約100万枚(原料は全部国産)
・日本での加工は月に3~4万枚程度
・残りの70万枚は海外に皮の状態で出荷され、なめされた後また日本で流通する
・海外での加工地は中国、台湾、韓国フィリピン、スロベニアなど
あとはMATAGIプロジェクトのことについて話されました。
それでは工場内へ。
工場見学は基本的に作業が終了した金曜日の15時からのため、実際の作業を見るわけではないです。
工場内の一番入口に近いところに置いてあったのがこのイノシシやシカの皮。
こちらはMATAGIプロジェクトで使用されるものです。地方の猟師さんが一枚一枚手作業で皮から肉を剥ぎ、腐らないように塩漬けして(塩をもみこむ)山口産業に原皮を送ってきます。
写真を撮り忘れましたが、この原皮の横にドラムがあり、そのドラムで大量の水を使い塩や血などの汚れを落としていきます。
タンナーでは用途別・工程別にドラムを使い分けています。
これが使用するドラムです。太鼓とも呼ばれます。なんと木製なんです。それどころかこの工場、基本的に木製なんです。これは温度変化を抑制することを目的としています。金属だと冷えすぎてしまい革の品質に影響が出るので、木を使用しているそうです。
そういった説明を受けながら次は2階へ。
2階は仕上げ工程が終わった革が干される空間になっていました。
上にかかっているは全て豚革です。この日はたまたま全部黒く染め上げていたようですが、日によってはカラフルな日もあるようです。ちなみにこの黒い豚革は吉田カバンで使われるそうです。
上にも豚革、目の前にも豚革。机の上には大きなピッグスキンが広げられています。
この豚革は山口産業独自のなめし方法「ラセッテー(RUSSETY)なめし」によるものです。
なめし材にはミモザアカシアの樹皮から抽出した植物タンニンを使用しており、クロム剤は一切使っていないのにもかかわらず、あたかもクロムでなめしたかのようなしなやかさを持っています。
もともとはクロムなめしもしていたようですが、2015年4月に国産のクロム剤がなくなったことをきっかけに、完全にラセッテーなめしの生産にシフトしたようです。
その後別室でパンフレットの表紙にもなっている「レザーサーカス(LEATHER CIRCUS)」というMATAGIプロジェクトに連携した事業のPRビデオを鑑賞しました。その部屋にはMATAGIプロジェクトでなめされた革が飾られていました。その中の1つがこの熊革。
さすがに熊の皮をなめすことになるとは思ってもいなかったようです。
そして質疑応答して工場見学は終了。
みなさんの熱心なので1時間だった予定を20分も過ぎてしまいました。
工場見学については以上です。
MATAGIプロジェクトについて
今回の工場見学で非常に興味深かったのが、このMATAGIプロジェクト。
地方で駆除されてしまったイノシシやシカなどを革に加工し、産地に返して製品化することで、資源を有効活用し地域の活性化を図ろうというプロジェクトです。
通常駆除されたイノシシやシカはそのまま処分されてしまいます。そうではなくて革にすることで、生きてきたことにしっかり意味を出してあげられる。素晴らしいプロジェクトだと思いました。
下の写真は代表の山口さんが首からかけられていたレザーのパスケースです。
これはMATAGIプロジェクトを利用し、岡山県吉備中央町で駆除されたイノシシの革を利用して作られたものです。
とてもかっこいいと思いませんか?
岡山県の法人では、駆除したイノシシの革を利用したブランドとして「KIBINO」というブランドを打ちだしました。どれも素敵な商品ばかりです。
イノシシの革はとても独特な雰囲気で、他のどの革よりもワイルドな雰囲気を醸し出します。
上はウリボーの革、下は大人のイノシシの革です。
ウリボー
イノシシ(成獣)
硬い毛を支えるため、革も非常にしっかりしています。
駆除した獣をそのまま捨ててしまっている自治体、猟師の皆様、もったいないと思いませんか?
是非こういったプロジェクトを活用してみてはいかがでしょうか。
詳細は山口産業のホームページに乗っています。
まとめ
なめしの勉強のためにと行った工場見学でしたが、いろんなことを勉強させていただきました。現在の豚革の原材料事情、なめし業者を取り巻く業界事情、MATAGIプロジェクトを始めとする環境への取り組みなど、本当に行ってよかったなと思いました。
開催がだいたい3、4週目の金曜日ですので会社員の方は休みを取らないと行けませんが、興味のある方は是非足を運んでみるといいと思います。自分の目で見て、耳で聞いて、鼻で感じ取った現場の雰囲気はきっと忘れられない思い出になることでしょう。
見学先情報
- 山口産業株式会社
- 〒131-0042
- 東京都墨田区東墨田3丁目11番10号
- TEL:03-3617-3868
- ホームページ:http://e-kawa.jp/

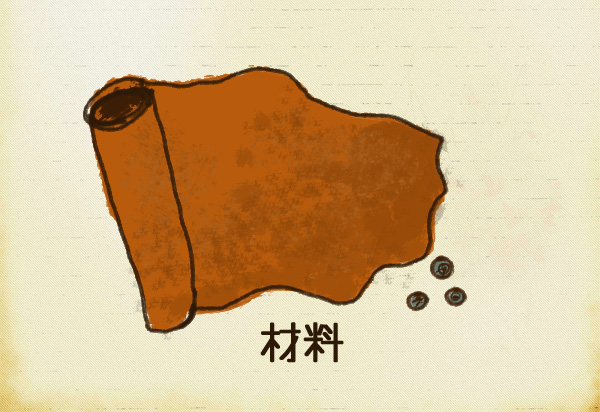












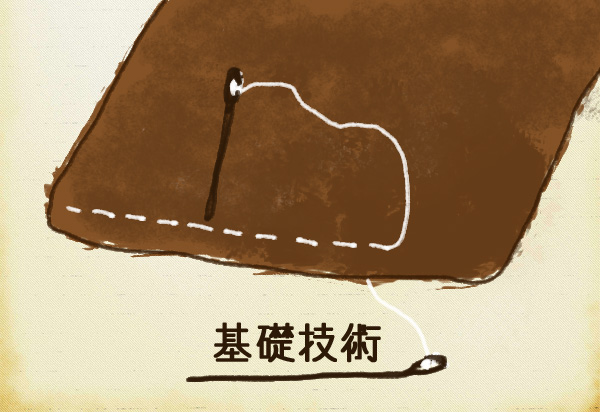

コメント